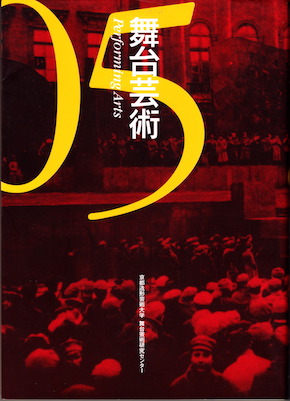
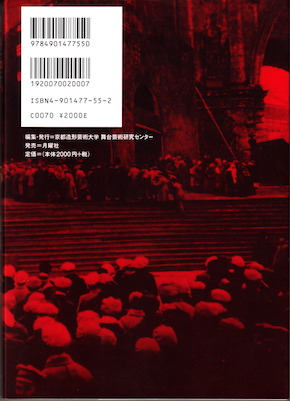
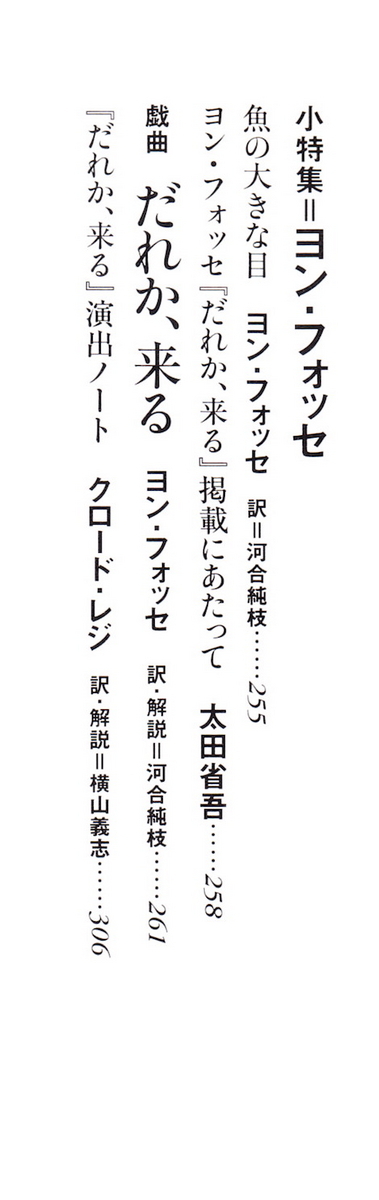
今年度のノーベル文学賞を受賞した、ノルウェーの作家ヨン・フォッセの戯曲『だれか、来る』(『舞台芸術5』月曜社)を読んだ。読み始めればすぐ「ベケットか」と思うが、最後まで読むととうぜん違うところがあるのに気がつく。『ゴドーを待ちながら』では結局はゴドーは現われなかったが、「だれか、来る」と予感する女にとって不安でもあり希望でもありあるいは何かである相手の「だれか」はほんとうに、西海岸のフィヨルドにある家を新しく買ってそこへやって来た50歳代の肥り気味の男と、比較的背が高くセミロングの髪の30歳前後の女、この二人の前に出現するのである。この家の売り主、住んでいて亡くなった老女の孫であった。
訳者河合純枝さんの解説によれば、ヨン・フォッセが執筆で使用する言語は、標準ノルウェー語ではなく、西海岸地区で使われるニュノルスク(新ノルウェー語)で、これは方言としての土着性に固執してのことではなく、話し言葉としてもつサウンドとか流れを重視してのこと。むしろ一種の人工言語といえる。さらに会話に反復性があるのも特色で、「二人きりで 一緒╱二人きり お互いと╱二人きり 互いの中に」(英語訳)「Alone together╱Alone with each other╱Alone in each other」とか。これは、フィヨルドの波の反復運動と、音楽のリズム形式としての反復という二つの側面があるとのこと。フォッセはロックのギタリストであった過去をもち、またヴァイオリンでクラシックも演奏するほど音楽に通じている。
そのどの反復表現も、互いにしがみつき、二人きりになりたい願望を、さざなみから大波へと盛り上げる。最後には、「互いの中に」合体を望む悲壮なまでの人間の姿が浮かび上がる。しかしやはりAloneなのだ。このAloneの中に、すべてを捨ててきた二人がただここに二人きりという意味と、なおかつ二人でいながらも、やはり個々人一人なのだというヨーロッパ文化の中にある゜個の単独性゛が重なる。(p.304)
登場人物のアイデンティティおよび属性などは極力省略されていて、抽象的な人格と人格とが向かい合い、反復的な会話を進める。このまま終了するのかと予想すると、「来た」だれかが、入った祖母の家の部屋で女に自分の電話番号を書いたメモを渡すと、女は拒否せず受け取って財布の中にしまう。目撃した男は嫉妬に苦しむが、女は平然としている。この辺は面白い。その前にだれかは、窓辺に寄っている女の腰あたりに視線を向けるが、女は知らない風情。抽象的な関係のちょっとした隙間に艶かしい一面を挿入、巧みである。
ノルウェー西海岸では同解説によれば、「その家々は、一軒ずつ散り散りばらばらに孤独な自然の中に散在し、隣家は2キロも3キロも先というのが通例」だそうで、電話番号のメモをくれた「だれか」も相当離れたところに住んでいるわけだ。大自然の中の孤独、人と人との関係における孤独、と孤独が重層的に存在している。ことばの反復的なキャッチボールの底にある「沈黙の有意味性』(吉本隆明)は、この孤独あってのこと。『ゴドーを待ちながら』よりも愉しめた。