
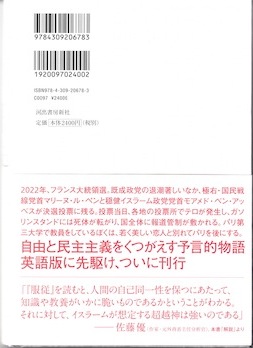
ミシェル・ウエルベックの小説『服従』(大塚桃訳・河出書房新社)を読みはじめる。ユイスマンスの研究家である大学教授の主人公が、ユイスマンスの人生と文学的実績について語りつつ文学一般のことを述べる。引き込まれた。ひさしぶりに現代小説を読む興奮を得られそうな出だしである。
……文学については、多くの、あまりにも多すぎる事柄が書かれてきた(この分野を専門とする研究者として、ぼくは他の者よりもそのように言う権利があると思う)。ぼくたちの目の前で終焉を告げている西欧の主要な芸術であった文学は、それでも、その内容を定義するのがひどく難しいわけではない。文学と同じく、音楽も、感情を揺さぶり引っくり返し、そして、まったき悲しみや陶酔を生み出すものと定義することができる。文学と同じく、絵画も、感嘆の思いや世界に向けられた新たな視線を生み出す。しかし、ただ文学だけが、他の人間の魂と触れ合えたという感覚を与えてくれるのだ。その魂のすべて、その弱さと栄光、その限界、矮小さ、固定観念や信念、魂が感動し、関心を抱き、興奮しまたは嫌悪を催したすべてのものと共に。文学だけが、死者の魂ともっとも完全な、直接的でかつ深淵なコンタクトを許してくれる。……(pp.8~9)
「ぼくたちの目の前で終焉を告げている西欧の主要な芸術であった文学」との認識と絶望を基底にもたない文学的営為は、いまや無効であろう。「男にとって愛とは与えられた快楽に対する感謝に他ならず、ミリアムほどの快楽を与えてくれる娘はいなかった」と述懐するそのミリアムとの官能と愛の関係も終わり、西洋民主主義について「対立するギャングが権力を分け合うに過ぎないこの選挙システム」と唾棄する主人公は、さてこの後どのような人生を生きるのであろうか、読み進めよう。